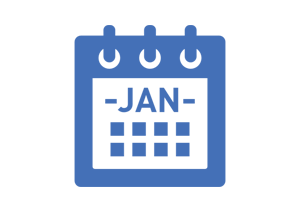 録画映像を見る
録画映像を見る
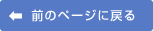
令和 2年第3回定例会(第2日 9月 3日)
| 録 画 中 継 | 会 議 の 内 容 |
|---|---|
|
再生速度(0.5倍速〜3.0倍速):1.0
|
間瀬 友浩(東海市民の声)
1 子どもの養育支援の充実について 1 兵庫県明石市では、平成26年4月にまちの未来である子どもの健やかな成長を市全体で応援するため、子どもの健全育成に多大な影響を与える離婚や別居時等における子どもの養育を支援する事業を実施している。また、愛知県都港区では令和2年4月に子どもへの心理的、経済的な負担を和らげるよう支援する事業を始めている。離婚や別居時等においても子どもの利益が最優先されるような環境を整備するべきだと考えるが、離婚時等の相談体制の状況及び今後について、本市の考えを問う (1) 離婚の届け出があった場合、今後の子どもの養育について、法務省発行の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」の活用状況を含めて、どのような対応を実施しているのか (2) よろず相談で離婚や別居に関する相談を受けた場合、今後の子どもの養育について、行政及び関係機関相互の連携状況を含めて、どのような対応を実施しているのか (3) 離婚や別居に伴う子どもの養育支援について、兵庫県明石市の市民相談室や愛知県都港区の子ども家庭支援部が総合的に取り組んでいるが、本市でも相談から支援まで総合的な対応ができる体制を構築する考えはあるか 2 両親が離婚し、片方の親の支えを失う子どもが、全国で毎年約20万人も増え続けている。なかにはDVや虐待の経緯がないにも関わらず、片方の親等が無断で子どもを連れ去り、もう一方の親の祖父母を含めた親族との関係が断絶されていることもある。夫婦の関係に関わらず子どもにとってはかけがえのない両親である。「日本一子育てしやすいまち」を目指す本市において、子どもの健やかな成長と発達に向けて養育支援を充実させる必要があると考えるが、子どもの養育支援の状況及び今後について、本市の考えを問う (1) 離婚に伴う子どもの養育支援について、本市ではどのような支援を実施しているのか (2) 厚生労働省が公表した「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」において面会交流の取り決めをしているのは母子世帯では24.1%、父子世帯では27.3%となっており、兵庫県明石市及び愛知県都港区の面会交流の仲介支援のように子どもの健やかな成長に向けて面会交流の取り決め及び円滑な実施を促すような支援を検討してはどうか (3) 兵庫県明石市が配布している「こどもの養育に関する合意書」、「こども養育プラン」及び「こどもと親の交流ノート」のように、両親に子どもの利益を最も優先するよう意識付けができる取組を検討してはどうか 2 行政における新しい仕事様式について 1 内閣府、法務省及び経済産業省の連名で令和2年6月に、押印についての指針であるQ&Aが公表され、押印慣行の見直しを勧めている。また、新型コロナウィルス感染防止のために在宅勤務を実践する事業者が増え、働き方改革の気運が益々高まっている。これらのことから「新しい生活様式」と同様に「新しい仕事様式」の実践に向けた絶好の機会だと考える。そこで今後の行政における「新しい仕事様式」について、本市の考えを問う (1) 内閣府、法務省及び経済産業省の連名で公表された押印についてのQ&Aについて、どのように捉えているのか (2) 行政における押印の代替手段の一つとしての電子署名を活用したオンライン申請を活用することについて、どのように考えているのか (3) 行政上の申請手続きについて、電子署名を含めたオンライン申請ができるような環境整備を推進してはどうか (4) オンライン環境を整備することで、「新しい仕事様式」の実践に向けて、職員の在宅勤務が更に進むような環境に整備してはどうか 3 ICTを活用した学校教育について 1 令和2年3月から小中学校が休業となり、6月に学校が再開されたが、新たな感染症の発生等の危機の到来も想定される。危機が過ぎ去り、平常に戻ることを待つのではなく、今後の学校の在り方を見直す絶好の機会と考える。令和3年4月に小中学生一人一台のタブレット端末導入に向けて取り組んでいるところだが、ICTを活用した学校教育の状況と今後について、本市の考えを問う (1) 文部科学省から毎年、公表されている「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」について、小中学生一人一台のタブレット端末が導入される予定の令和3年4月時点で本市はどのような状況になる見込みなのか (2) タブレット端末の導入にあたり、家庭での学習や長期の臨時休業となった場合に、タブレット端末を持ち帰りMicrosoft Teams等のクラウドサービスを遠隔授業や家庭学習で活用する考えはあるか (3) タブレット導入後、教員用及び児童生徒用の電子教科書の導入について、どのように考えているのか (4) 小中学校の校外学習や体験学習に参加できない児童生徒に向けて、学習方法の選択肢としてタブレット端末を活用した遠隔学習ができるような体制を構築してはどうか。また、長期入院のために院内学級に通学している児童生徒も遠隔学習ができるように県に働きかけてはどうか (5) ICTを活用した遠隔合同授業を実施している愛媛県西条市を参考として、学校間の交流や教員の授業力を高めるために、各小中学校の経験豊かな教員による遠隔合同授業を実施する機会を設けてはどうか 4 高齢者のICT活用支援の充実について 1 総務省は令和2年3月に、高齢者等がICT機器やサービスの利用方法を、身近な場所で身近な人に気軽に相談できるデジタル活用支援員について検証するためにデジタル活用支援員推進事業地域実証事業を公募し、名古屋市等が採択先候補として決定された。今後、益々ICT化が進む情報社会で高齢者を孤立させないために更なる支援が必要だと考えるが、高齢者のデジタル活用支援の現状と今後について、本市の考えを問う (1) 社会のICT化が進む中で、高齢者にどのようなICT関係の支援を実施しているのか (2) 高齢者のICT活用の推進に向けて、どのような課題があるのか。また、課題解決のためにどのような取組を実施しているのか (3) 今後のICT支援の在り方を検討するために、高齢者世帯のICT環境を調査してはどうか (4) 通信事業者と連携し、本市独自の施策として、各地域にデジタル活用支援員を配置してはどうか。また、国の実施するデジタル活用支援員推進事業地域実証事業に、今後参加する考えはあるか |

 録画映像を見る
録画映像を見る