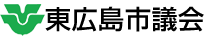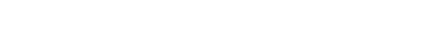過去の本会議の録画映像を御覧いただけます。
令和 6年第3回定例会(第3日 9月10日 一般質問)
答弁山田 学
1 食育の取り組みについて
(1) 給食時における黙食について
コロナ禍を経て学校給食での黙食は必要なくなったが、感染症対策が目的ではなく、食品残渣を減らすというねらいで黙食を続けている学校がある。給食時間は食を通じてコミュニケーション能力や協調性を養える大切な学びの時間である。食品ロス対策は必要だが、本来の目的とは異なる理由で黙食を続けることに対して本市の見解を伺う。
ア 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定後も黙食を進めている学校があることについて、本市はどの程度把握しているか伺う。
イ 黙食で食品残渣を減らす対策は子供のコミュニケーションの時間を奪うことにつながり、国が推進している食育であるとは言い難い。食品ロス改善のための黙食の実施について本市の見解を伺う。
ウ 児童同士が向き合って食べる「グループ給食」にはコミュニケーション能力や協調性を養う以外にも、誤飲や窒息事故などの給食時の事故防止の観点でも重要であると考える。全校でのグループ給食再開についての見解を伺う。
(2) 食育支援事業について
健康で豊かな食生活の実現を目的に文部省、厚生省(当時)及び農林水産省により策定された「食生活指針」では、「主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」を一つの指針として、それを実践するには「多様な食品を組み合わせましょう。」としている。また、「食生活指針」を具体的に行動に結びつけるものとして厚生労働省と農林水産省が決定した「食事バランスガイド」を参考にして、副菜をスーパーやコンビニなどで購入している家庭も多い。一方で、現代の市販食品には、必須微量ミネラルの摂取よりも、見かけだけの食品摂取バランスを追求しているものも多いように感じる。食卓のミネラル不足がさまざまな病気を引き起こす大きな原因になっているとも考えられる。講師による講演会の開催等、食品の成分や品質に言及した情報を伝える事が市民の食や健康への意識や理解を深めることにつながると考えるが、本市の見解を伺う。
ア 令和5年第2回定例会の添加物に関する一般質問の答弁にて、「食品表示を含む食品衛生に関する事項は広島県と連携を取りながら、情報提供の機会を確保することを検討する」とあったが、その後の進捗について伺う。
イ 外部講師を招いての食に関する講演会の開催の見込や過去の取り組み、実績について伺う。
ウ 第3次東広島市健康増進計画の今後の取り組みである「健康寿命の延伸につながる食生活の推進」には「食品の栄養成分表示等の活用について情報提供する」とあるが詳細について伺う。
(3) 学校給食の有機農産物活用に向けた取り組みについて
令和6年度の学校給食センターの運営に「有機野菜活用の試行的取り組み」として90万円の予算が割り当てられた。これは地場産物の活用のために、量の確保ができるよう産業部や農家関係機関と連携し、学校給食における有機野菜の利用促進を図るもので、子供達の健康を願う保護者の方からも大変期待されている。その後の進捗と今後の取り組みについて伺う。
ア 令和6年度の学校給食センターの運営にある「有機野菜活用の試行的取り組み」の進捗状況と現状の取り組みと課題、評価について伺う。
イ 令和5年第2回一般質問にて、オーガニックビレッジについて質問した回答で、「販売者、消費者を交え、様々な立場の方から意見を聴きながら検討をしていく」とあったが、検討内容と進捗状況を伺う。
ウ 学校給食で積極的に有機米を使っている自治体が増えている中で、本市での学校給食での有機米の使用の今後の可能性と課題について伺う。