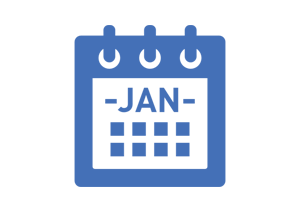 録画映像を見る
録画映像を見る
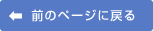
令和 7年第2回定例会(第2日 6月19日)
| 録 画 中 継 | 会 議 の 内 容 |
|---|---|
|
再生速度(0.5倍速〜3.0倍速):1.0
|
工藤 政明 議員(市友会)
1 災害に強いまちをつくる取組について 1 令和7年3月31日に内閣府中央防災会議の有識者会議は、南海トラフ地震が発生した場合の新たな被害想定を公表し、犠牲者の数の最大は平成24年に公表した約32万3千人から減少したものの約29万8千人という甚大な被害となる可能性があることを示している。これにより、南海トラフ地震に対する市民の関心は大きく高まったと想像する。南海トラフ地震の被害想定及び対策について、本市の状況と考えを問う (1) この度と平成24年に公表した被害想定の違いをどのように把握しているのか。また、犠牲者の数が最大となる地震発生の時期及び気象条件等はどのようなものなのか (2) 本市内の最大震度や津波の最大高さ及び最短到達時間をどのように把握しているのか。また、その数値はこれまでの想定と変化はあるのか (3) 国は被害を軽減させるため、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を改定する動きを示しているが、改定する時期や方向性をどのように把握しているのか (4) この度の新たな被害想定の公表を受けて、市民へ大地震から身を守るための注意喚起等の周知・啓発を改めて行う必要性があると考えるが、周知・啓発の時期等進め方をどのように考えているのか 2 本市を含む愛知県は、南海トラフ地震が発生した際には大きな被害が出ることが想定されており、その犠牲者の多くは建物倒壊によるものとされている。建物倒壊による被害の軽減が期待できる住宅の耐震化について、本市の状況と考えを問う (1) 住宅耐震化率の算出方法はどのように定められているのか (2) 住宅耐震化率は調査年度毎に改善を示しているが、その理由をどのように把握しているのか。また、住宅の耐震化を促進するための問題点や課題はどのように整理され、対応策は立案されているのか (3) 令和7年度に予定されている建築物耐震改修促進計画策定事業の事業内容はどのようなものなのか (4) 耐震性が不十分な住宅に防災ベッドや耐震シェルターを設置した場合は、耐震改修工事が施されていると見なすことになるのか 2 水道水の安全安心を確保する取組について 1 普段の生活で1日に1人で約300リットルの水を使用することから、水道水は暮らしに欠くことの出来ない大切なものである。最近では、家電製品をはじめ家庭で使用する様々な機器において節水型の普及が進んでいるところではあるが、限りある資源でもある水源から供給される水道水の重要性を市民に理解・啓発する取組について、本市の状況と考えを問う (1) 令和5年度における本市の水道水の使用量は1日1人283リットルとの報告があるが、近隣市町の使用量をどのように把握しているのか。また、差の要因をどのように考えているのか (2) 節水の実施は水源の貯水量等の条件により異なると想像するが、愛知県営水道から本市への節水対策はどのように示されるのか。また、本市の水道水の利用者にはどのように示され、節水に努めることになるのか (3) 本市には愛知用水と長良導水の2水系から給水を受けているが、節水対策に水系による違いはあるのか (4) 普段から水道事業への理解・啓発を促すことが重要と考えるが、日頃からの水道事業に関する市民への理解・啓発する取組はどのように行われているのか 3 野良猫と地域の共生を目指す取組について 1 野良猫と呼ばれている特定の飼い主がいない猫を地域で適切に飼養・管理する地域ねこ活動について、本市の状況と考えを問う (1) 活動する団体の登録及び廃止の数をどのように把握しているのか。また、活動団体となるための登録や届出の要否及び活動内容の条件はどのように定められているのか (2) 団体が活動した効果及び団体が抱えている問題点や課題をどのように把握しているのか (3) 県、市及び地域ねこ活動団体は野良猫の引き取りや保護を行っていないとのことだが、野良猫が自宅敷地内等で子猫を産む等で野良猫の引き取りや保護を望む市民に対し、本市はどのような対応を講じているのか (4) 猫の避妊及び去勢の手術経費をどのように把握しているのか。また、活動団体が手術費用を賄う方法をどのように把握しているのか (5) 令和6年度の猫避妊等手術費補助金の交付実績はどのような状況なのか (6) 市に登録している活動団体はどのような支援策を受けることが出来るのか。また、活動に見合った補助金の交付等、支援策を充実する必要性をどのように考えているのか 4 自動車等運転資格の適切把握の取組について 1 出張をはじめとする勤務で自動車等を運転する職員が取得している運転資格の把握について、本市の状況と考えを問う (1) 勤務で自動車等の運転が必要となる職員は何名か。また、全職員に対してどのような割合になるのか (2) 職員が取得している運転免許証の種類や有効期限等の確認はどのような方法及び頻度で行われているのか (3) 運転免許証の現物確認はどのように行われているのか。また、マイナ免許証に記録された免許情報を確認する方法は整えられているのか (4) 自動車等の運転資格の確認は、運転免許証の取得後もしくは更新後に所属長等が免許証の現物を確認し運転資格の把握に務めるべきと考えるが、そのような方法を採用する必要性をどのように考えているのか 5 救急要請に迅速に対応する取組について 1 令和4年から3年連続で過去最高を更新する等かねてから救急出場の件数は高い水準が続いている。絶え間なく寄せられる救急要請に応じる救急出場及び救急隊員の活動について、本市の状況と考えを問う (1) 令和6年の救急出場における現場到着所要時間及び病院収容所要時間はどのような状況なのか。また、令和元年以降はどのような推移を示しているのか (2) 現場到着所要時間及び病院収容所要時間を短縮する取組はどのように行われているのか (3) 市内には自動車専用道路が3路線通っているが、本市消防本部の管轄はどのように定められているのか。また、路上等で活動する救急隊員を交通事故から守る取組はどのように行われているのか (4) 救急隊員の精神的かつ肉体的な負担を軽減させる取組はどのように行われているのか。また、負担軽減のために、市民に理解や協力を呼び掛けるものはあるのか (5) 救急隊を強化もしくは高度化する必要性をどのように考えているのか |

 録画映像を見る
録画映像を見る