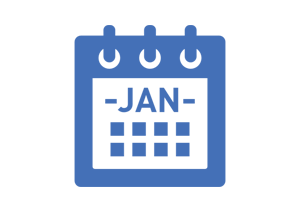 録画映像を見る
録画映像を見る
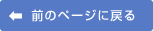
令和 6年第2回定例会(第1日 6月13日)
| 録 画 中 継 | 会 議 の 内 容 |
|---|---|
|
再生速度(0.5倍速〜3.0倍速):1.0
|
工藤 政明 議員(市友会)
1 公共交通の安全安心を確保する取組について 1 令和6年3月に市内で9駅目となる加木屋中ノ池駅が開業し、知多半島内で名古屋鉄道の駅が最も多い自治体となり、鉄道と市民生活の関わりが更に深くなったと言っても過言ではない。鉄道が安全で安心に利用出来る環境を整える取組について、本市の状況と考えを問う (1) 駅集中管理システムが8駅に導入され、実質的に終日無人駅となったが、導入目的をどのように把握しているのか。また、駅を利用する市民への影響をどのように考えているのか (2) 踏切道の設置数及び種類をどのように把握しているのか。また、踏切道の利便性向上及び安全確保等の方向性をどのように考えているのか (3) 市内全ての駅が列車通過駅となっているが、列車の通過速度及び駅利用客の安全確保策をどのように把握しているのか (4) 駅のホームドア設置が望まれるが、国や県の設置方針や補助制度等をどのように把握しているのか。また、とりわけ、名鉄太田川駅への設置を鉄道事業者へ要望するべきと考えるがその必要性をどのように考えているのか 2 令和6年10月から運行ルート等の再編が計画されている市内循環バスは、利便性の向上に期待が寄せられるとともに、安全安心な利用環境の確保が求められている。循環バスが安全で安心に利用出来る環境を整える取組について、本市の状況と考えを問う (1) 令和6年度の乗車延べ人数の増加をどのように見積もっているのか (2) 車内で発生した乗客間もしくは乗務員とのトラブルはどのようなものがあるのか。また、運行事業者が施しているトラブル防止策をどのように把握しているのか (3) 令和5年度から運行を開始したEV車両の導入効果は、事業計画に沿ったものを得ることができているのか。また、問題点や課題はどのように整理され、対応策は立案されているのか (4) 10月から現行の6台から8台体制へ車両の増強を計画しているが、バス運転手不足問題への対応策をどのように把握しているのか (5) 市内をくまなく走行する特性を生かして、道路及びその周辺の異変や瑕疵等の情報を収集し、改善につなげる仕組みを構築する必要性をどのように考えているのか 2 豊かな水環境の維持に向けた取組について 1 本市が面する伊勢湾において、工場等に対する排水規制や重点的な下水道整備と下水処理技術の向上により公共用水域の水質保全が図られる一方で、漁業生産に必要な栄養塩不足によるノリやアサリの生育への影響が心配されている。きれいだけでなく豊かな水環境を求める漁業関係者等からの要請に基づき、令和4年度及び5年度に取り組んだ浄化センターにおけるリン濃度増加管理運転について、本市の状況と考えを問う (1) 管理運転に取り組む前のリンの排水基準及び排水実測値はどのような状況なのか (2) リン放流に至った経緯をどのように把握しているのか。また、管理運転はどのように行われたのか (3) 伊勢湾に面する近隣浄化センターが行った管理運転の状況をどのように把握しているのか (4) 管理運転前後の水質及び生物の生態調査結果をどのように把握しているのか (5) 管理運転の結果を踏まえた管理運転継続もしくはリンの排水基準変更等の国や県の見解及び方向性をどのように把握しているのか 3 熱中症の危険を強く呼び掛ける取組について 1 令和5年夏季の国内の平均気温が統計開始以来、最高を更新し、令和6年夏季も猛暑が予想される中、環境省は4月24日から10月23日まで、災害級の熱波に備えるため熱中症特別警戒アラートの運用を開始した。比較的温暖な気候とされる本市においても、気温が特に著しく高くなった際の熱中症対策は重要であると考えられることから、熱中症特別警戒アラート運用への対応について、本市の状況と考えを問う (1) 令和5年の熱中症を原因とする救急搬送はどのような状況なのか。また、搬送が集中する等の特徴は確認されているのか (2) 発表する目的及び条件並びに対象区域をどのように把握しているのか。また、本市が対象の区域となる可能性をどのように考えているのか (3) 発表された際の本市が行うべき対応はどのように定められているのか (4) 発表された際の小中学校における授業等の対応はどのように定められているのか (5) 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の設置状況はどのようか。また、指定施設や開放時間の拡大を図る必要性をどのように考えているのか 4 無線通信の障害を防止する取組について 1 2050年のカーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギー導入による脱炭素化を図る取組の具体策として、精力的に設置が進められている、太陽光発電システムを原因とする無線通信への障害が全国で多発しており、防災行政無線等の人命に関わる無線通信が障害を受けた事例も報告されている。無線通信は公共や民間を問わず幅広く使用され、市民の生活基盤を構築する重要な役目を担っている分野でもあることから、太陽光発電システムを原因とする無線通信の障害について、本市の状況と考えを問う (1) 住宅用太陽光発電システム及びメガソーラーと呼ばれている出力が1メガワット以上の施設の設置状況をどのように把握しているのか (2) 無線通信障害の原因と影響をどのように把握しているのか (3) 無線通信障害を認知した場合の相談が市民から本市に寄せられた際の対応策は立案されているのか (4) システムの設置事業者等へ注意を喚起もしくは対策を促す必要性をどのように考えているのか 5 食品ロスを削減する取組について 1 まだ食べられる食品が廃棄されている食品ロスが生産から消費までの各段階で発生し、その量の多さが国際的な問題として認識されるとともに、その削減が重要な課題となっている。食品ロスを削減する取組について、本市の状況と考えを問う (1) 2000年度における家庭系及び事業系の食品ロス発生量をどのように把握しているのか。また、発生量の把握はどのような方法と頻度で行われているのか (2) 発生元や発生原因をどのように分析しているのか (3) 食品ロス問題を認知して削減に取り組む市民の割合をどのように把握しているのか。また、食品をごみにしない行動の啓発や周知はどのように行われているのか (4) 国と県は2030年度までに2000年度に比べて食品ロスを半減する目標を掲げているが、本市の目標はどのように定められているのか (5) 2030年度に向けて市民、事業者、行政に求められる役割と行動を明確に示した中長期的な取組を立案する必要性をどのように考えているのか |

 録画映像を見る
録画映像を見る