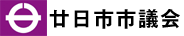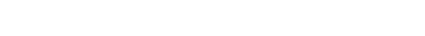過去の本会議の録画映像を御覧いただけます。
令和 6年12月定例会(12月 6日) 日程第2 一般質問
大畑 美紀(日本共産党市議団)
1 地方自治体の公共と自治の行方は地方自治や地域がどうなるのかは国の政策によって大きく左右される。新自由主義的な政策により、公共が縮小、自治は後退し、過疎の進行など、地域や市民の暮らしを脅かしている。「官から民へ」の政策は、低賃金労働者を増やし、暮らしと社会の不安定化に手を貸している。石破首相は所信表明演説で「地方創生を再起動させる」と述べた。首相は2014年から始まった「地方創生」の初代担当大臣であるが、地方創生に掲げた「東京一極集中の是正」と「合計特殊出生率引き上げ」は達成できず、さらに悪化している。デジタル化や地方創生交付金の増額では根本的な問題は解決できないのではないか。また、2024年6月に成立した改正地方自治法は「国の地方自治体への指示権」を閣議決定のみで発動できることを規定しており、「国が地方を支配できる仕組み」を作るものとして、日本弁護士連合会から反対の会長声明が出され、首都圏自治体の首長・議員でつくる「ローカルイニシアティブネットワーク(略称LIN−Net)」ほか多くの団体からも、改正に反対し改正部分の廃止を求める声が上がっている。国の政策を無批判に受け入れるのではなく、地方自治体の自治を発展させ、公共を再生することで、市民の暮らしと地域を守ることに繋げていくことが重要と考え、次の点を問う。
(1)指定管理者制度やPFIほか「自治体アウトソーシング」の手法を検証し、見直すべきではないか。
(2)本市における「地方創生」はどうあるべきと考えるか。
(3)改正地方自治法が市政に与える影響についての見解は。
2 障害者権利条約にふさわしい障がい者施策を
日本は障害者権利条約の批准国であるが、2022年に権利委員会から日本政府に対し勧告(総括所見)が出され、課題が指摘されている。障害者権利条約の大きな柱「障害のない市民との社会的平等」「合理的配慮をおこなわないことは差別である」などが十分に生かされていない現状がある。介護保険優先原則により、65歳からの介護保険への強制移行で実費負担増や必要なサービスが受けられない問題がある。親亡き後の生活の場を住み慣れた地域に求めても得られないことも少なくない。また、生活介護などの障害福祉サービスは今年4月の報酬改定で日額払いから時間払いに変更され、大幅に減収になる事業所が出ている。食事提供には食事提供体制加算300円の基準があるが、人件費と物価高騰分を賄えずマイナスになると聞く。新型コロナの5類移行後も施設においてクラスターが発生することがあるが、2類の時にはあった特例がなくなり、減収が大きな痛手となっている。職員不足と物価高騰という厳しい状況は障がい者支援の質の低下を招くおそれがある。このまま放置すれば、事業所の存続、支援体制が危機的な状況になることが予想される。廿日市市障がい福祉計画、廿日市市障がい児福祉計画の基本的視点が施策に実現できるよう、基本合意(2010年)、骨格提言(2011年)、障害者権利条約(2007年署名、2014年締結)を尊重した施策を求めて問う。
(1)福祉を担う人材不足の大きな要因は低賃金にある。福祉現場で働く職員の賃金改善のための市独自の人件費補助等の施策実施を(例えばヘルパー養成の研修や補助、時間割報酬への上乗せ、相談員の報酬上乗せ、広島市が行っているようなグループホームの重度障害者受入促進補助など)。
(2)クラスター発生時や災害時などの長期休みによる減収への補填を。
(3)グループホーム利用者への家賃補助拡大を。
(4)グループホームが足りない。親亡き後を踏まえた地域の生活の場確保策は。
3 緑地の保全と環境施策について
2024年5月改正都市緑地法が成立した。改正内容は、緑地保全のための規制強化でなく、緑地を一定程度確保すれば大規模な再開発を可能とする規制緩和である。各地で街路樹や公園の樹木の大量伐採が問題となっているが、本市では沿岸部の緑地の多くが開発によって失われようとしている。改正緑地法は廿日市市緑の基本計画や環境施策にも影響を与える。本市では、生産緑地の新たな指定を行うとしている。環境都市宣言、ゼロカーボンシティを宣言した本市として、樹木や、都市農地も含めた緑地の保全は必要不可欠であることから、次の点を問う。
(1)生産緑地制度により本市の都市農地と環境が守れるのか。
(2)新機能都市開発ほか沿岸部の開発で多くの山林がなくなることの影響をどう捉えているのか。
(3)目標年次を2025年度としている廿日市市緑の基本計画の見直しはあるのか。