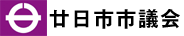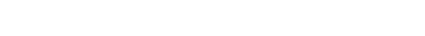過去の本会議の録画映像を御覧いただけます。
令和 5年 9月定例会( 9月12日) 日程第2 一般質問
向井 恵美(新政クラブ)
1 老老介護等における介護者への負担軽減策について日本人の2022年平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳となっている。2019年の統計による健康寿命は、男性が72.68歳、女性が75.38歳であり、健康寿命から平均寿命までの期間が要介護となる可能性が高い期間ということになる。厚生労働省「国民生活基礎調査2022」の調査結果によると、要介護者と同居の介護者の年齢の組み合わせをみると、65歳以上同士の割合は、2001年40.6%から2022年には63.5%に増加、75歳以上同士の割合は、2001年18.7%から2022年には35.7%へと増加している。また、介護する方の状況をみると、同居家族が45.9%介護しており、そのうち配偶者が22.9%で最も高く、次いで同居の子が16.2%などとなっている。本年5月に東広島市で「自宅で衰弱の老夫婦、市が安否確認を2度怠る、事態を把握したのは救助の4日後」という報道があった。80代の夫婦が自宅で衰弱し、宅配弁当業者が見つけて救助に繋げた案件で、市の地域包括支援センターが宅配弁当業者から2度連絡を受けながら安否確認をしていなかった。また、少しケースは異なるが、子どものひきこもりが長期化し、周囲から孤立したまま、親が80代、本人が50代といった状態に陥る「8050問題」を含め介護者の身体的な負担が継続すると先の見えない気持ちに襲われ、精神的な負担も大きくなると思われる。核家族が増え、身内に頼ることにも抵抗感を感じる人は少なくないと思っており、他人に頼ることは尚更躊躇していると思われる。本市においても、高齢者の一人世帯、二人世帯は、多くなっていると思うが、民生委員・児童委員や地域包括支援センターの方々による状況把握に努められていると認識している。そこで、次の2点について問う。
(1)老老介護世帯の生活環境、件数などきめ細かな状況把握について、どの様な方法で行っているのか。また、課題等はあるのか。
(2)「やすらぎ支援事業」など実施していることは承知しているが、更なる介護者への身体的、精神的な負担軽減する施策を考えているのか。
2 自転車の安全運転、マナーアップについて
先般、新聞に「悪質自転車の反則金方針」という記事が掲載されていた。警察庁が自転車で交通違反した人に、自動車やバイクのように交通反則告知書、いわゆる交通反則切符を交付できる道路交通法改正を目指す方針とあった。反則金導入でルール順守の意識が向上し、交通安全の確保に向けた大きな一歩であると強調されていた。自転車の運転に関しては、過去に傘さし運転、携帯電話・スマホ、イヤホン、ヘッドホンを使用しながらの運転は禁止されていた。今年の4月からは「ヘルメットの着用努力義務化」が施行されている。自転車は、道路交通法上で軽車両と規定されており、歩道の通行要件の見直しなどもされているが、未だに我がもの顔で歩道を走り歩行者が慌てて道を空けるケースが多々見受けられる。広島県の令和4年交通事故発生状況の統計をみると自転車が絡む交通事故による死者数6人、負傷者数880人となっている。総事故件数に対する自転車関連事故件数の割合は21%を占めている。毎年5月は、自転車マナーアップ強化月間、毎月1日は自転車安全運転の日と定めてルール、マナーの向上に努めているが、自転車安全利用五則が守られていないのが現状である。特に通行は車道が原則、左側を通行、歩道は例外で歩行者を優先とする。交差点では信号と一時停止を守って安全運転と定めている。車道を斜めに横断、横一杯に広がって走行するなど通行に関して順守されていない自転車の利用者を多々見受ける。市においても、マナーアップ強化月間を中心に自転車の安全運転に関しては、各種の機会を捉えて取り組んでいるものと思う。そこで、次の点を問う。
(1)本市内での自転車の絡む交通事故件数やその要因などを十分に把握し、マナーアップ啓発活動に繋げているのか。また、啓発活動は何処でどの頻度で実施し、その成果はどうか。