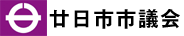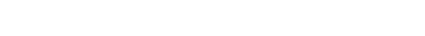過去の本会議の録画映像を御覧いただけます。
平成24年 3月定例会( 3月 9日) 日程第2 一般質問
細田 勝枝(公明党)
1 AED搭載自動販売機の設置及び普及促進の拡大についてAED(自動体外式除細動器)は、心疾患により突然心臓が止まった傷病者に除細動(電気ショック)を与え、心臓の働きを戻すものである。本市の公共施設である市役所、スポーツセンター、小・中学校、市民センターなどは、ほとんどが建物内にAEDを設置している。しかし、例えば各施設の周辺において心停止者が発生した場合、閉館時は使用できない。このような事態はいつ起きるか分からない。目の前にAEDを設置している公共施設があっても使えず、救急車を待たなければならないことになる。そこで次の点について問う。
(1)AED搭載の自動販売機の設置を推進すべきと考えるが見解を問う。
(2)24時間営業のコンビニエンスストアへのAEDの設置の普及促進の拡大について問う。
(3)学校における普通救命講習の実施について、教育長の見解を問う。
(4)AED設置状況マップの作成について問う。
2 地域住民の声をいかしたよりよい交通弱者対策について
吉和・佐伯地域で、利用対象地区の拡大、ルートや料金等、形態の見直しを図った交通再編計画として、昨年の12月よりデマンド型乗合交通の実証運行が始まり3か月がたった。交通弱者対策として昨年から実施しているデマンド型乗合交通であるが、これまでと大きく変わったことは、料金と、登録して予約の電話を入れるなどの利用方法である。それぞれ地域特性があり、喜びの声も聞くが、高齢者の多い地域で戸惑いの声もある。そこで次の点について問う。
(1)デマンド型乗合交通に対する利用者の反響はどうか、3か月たった実証運行の実態を問う。
(2)アンケート調査やこれまでの地域住民の利用者の意見や要望をどういかすのか問う。
(3)大野・廿日市地域の交通再編計画の今後の見通しと計画について問う。
3 「脳せき髄液減少症」の実態把握と今後の対応について
「脳せき髄液減少症」は交通事故やスポーツ外傷など、体への衝撃によって脳せき髄液が漏れ続け、減少することで脳が沈み込む病気である。この病気は、様々な痛みが出ることが大きな特徴で、頭痛、目の奥の痛み、視力障害、どうき、息苦しさ、腹痛、目まい、動揺感、ふらつき、腰痛、のどの奥の違和感、声がかれる、ものが飲み込みにくい、けい部、背部の痛みなど、様々な症状に慢性的に苦しめられる病気である。診断を受けても、うつ病、むち打ち症、起立性調節障害など、他の診断名を付けられ、適切なケアがされていないのが現状である。国内には、約30万人の患者がいると言われ、潜在的には病名も知らず苦しんでいるかたは100万人を超えると言われている。現在においても脳せき髄液減少症の認知は極めて低く、外見が健常者と変わりないことが多いことから、職場や学校において周囲から理解されず誤解を生じ、悩み苦しんでいるかたがいると聞く。そこで次の点について問う。
(1)本市のホームページにおいて、脳せき髄液減少症という病気をより広く多くの市民に周知するとともに、検査・治療が可能な医療機関や相談窓口、関連情報リンクなどを公開すべきと考えるがどうか。
(2)平成19年5月に文部科学省から「学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応について」通知が出されたが、これを受けて教育現場における関係者に対してどのような対応をしたのか、また、脳せき髄液減少症をどのように周知していくのかを問う。